和歌山の女性内科専用外来 。内科,脳神経内科,漢方外来,更年期障害,睡眠時無呼吸症候群,プラセンタ,各種ビタミン美容点滴,ファーストピアス,帯状疱疹ワクチン
電話でのご予約・お問い合わせはTEL.073-475-0010
〒640-8323 和歌山県和歌山市太田1丁目13-10 太田ビル3階
正しいダイエットDiet ただしいだいえっと
| プラセンタ療法 | 各種ビタミン | ダイエット外来 | ピアス穴あけ |
|---|---|---|---|
| 女性漢方外来 | 女性の睡眠障害 | ウエストまわり | 冷え性 |
正しい「ダイエット」とは
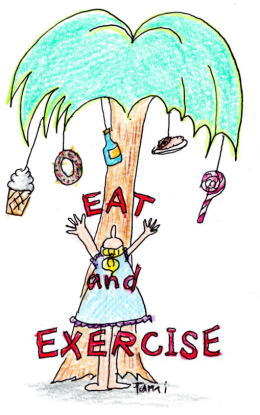 食事の量を制限し、エクササイズや運動して減量すること。
食事の量を制限し、エクササイズや運動して減量すること。極端な摂取制限は、リバウンドの恐れだけでなく健康に害を及ぼす。
本来、英語の「diet」は日常的な食事・食べ物を意味します。日本では食事の量や種類を制限する食事療法のほかに、エクササイズや運動して減量し、痩せた体型を目的とする「痩身」と同義に使われています。
一般的なダイエットは、運動や基礎代謝などで消費するエネルギーよりも、食事で摂取するエネルギーを少なくすることで体重を減らします。一日の基礎代謝量は、成人男性約1500キロカロリー、成人女性で約1200キロカロリーです。
極端に摂取を制限したり特定の食品のみ摂取する偏ったダイエットは、一時的には体重の減量が期待できますがストレスがたまるうえに必須栄養素の量が不足し、食物繊維不足による便秘、マグネシウムやビタミンD不足による骨粗鬆症、鉄分不足による貧血、月経異常など健康を損なう恐れがあります。
規則正しい生活を送り、食事ではカロリー計算をして、決して無理にならないようにカロリー摂取を調整しつつ、ウォーキングやランニングなど適度な運動を長く続けることが、ダイエットを成功させる秘訣です。
健康的なダイエット:適切な体重管理で、健康づくりをしよう!
 食生活や生活習慣が多様化した現在では、過食や運動不足による「肥満」や「メタボリックシンドローム」がある一方で、不健康なダイエットなどによる「やせ」も社会問題となっています。楽しく健康でいきいきと過ごすためには、適切な体重の認識と体重管理が大切です。
食生活や生活習慣が多様化した現在では、過食や運動不足による「肥満」や「メタボリックシンドローム」がある一方で、不健康なダイエットなどによる「やせ」も社会問題となっています。楽しく健康でいきいきと過ごすためには、適切な体重の認識と体重管理が大切です。20歳以上の男性で、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者は約2割、その予備群と考えられる者もさらに2割程度いることが、平成17年国民健康・栄養調査により報告されています。さらに50代以上の男性では、2人に1人の割合でメタボリックシンドロームが強く疑われる又はその予備群であることが示されています。
20歳以上の女性では、それぞれ合わせて約2割と男性の半分程度と少なめですが、一方で肥満度(BMI)が18.5未満の「低体重(やせ)」が20~30代で約2割と多いことが示されています。
日本肥満学会では、肥満度を示す指標として世界中で用いられているBMI(Body Mass Index:ボディマスインデックス)を使用し、BMI18.5未満を「低体重」、18.5以上25未満を「普通体重」、25以上を「肥満」と定義しています。また医学的に最も病気のリスクが少ないBMIを22として「標準体重」又は「適正体重」としています。
BMIは現在の体重(kg)を身長(m)の2乗で割ったものです。例えば現在体重が60kgで身長が170cmの男性の場合は、60÷(1.70)2でBMIは20.8となります。また170cmの男性の「標準体重」は22×(1.70)2となり、63.6kgになります。
平成17年の国民健康・栄養調査では、15歳以上の男女に「やせすぎや太りすぎでない体重を維持すること」についての意識調査をしています。その結果「改善したい」と思っている者の割合のピークは男女とも40代で、男性が53%、女性は58%。また男性は20代から増え始めるのに対して、女性はすでに10代後半で半数以上が「改善したい」と思っていました。一方で実際には男女とも20~30代では全体の7割が「普通体重」であるため、多くの者で適正な体重認識が出来ていないと考えられます。
適切なダイエットや体重コントロールは、まず自分にとってそれが本当に必要かどうか診断することから始めましょう。すでにBMI18.5以上で標準体重である22程度である場合、特別な体重コントロールは必要ありません。またBMIが25未満であっても、以前よりも体重が増加気味という方やすでにBMIが18.5未満又は25以上の者は、適正体重を達成するために食事の内容を見直しましょう。
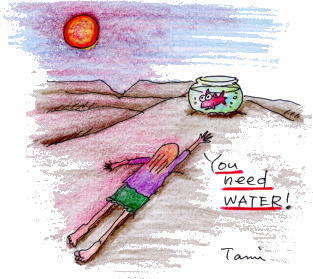 そしてダイエットを始める前に、食事記録をつけてみるのも良いでしょう。「水を飲んでも太る!」と考えている人ほど、無意識に食べている食品の多さに気がつくはずです。またダイエットや体重コントロールというと、すぐ極端に食事量を減らすことを考える方も少なくないと思いますが、食事のみよりも運動を併用するほうがより効果的です。食事内容を見直す上では、ご飯やパンなどの主食を減らしておかずを中心に食べる、ダイエット食品を利用するなどの偏った食生活ではなく、主食・副菜・主菜のバランスを考え、調理法や菓子・アルコールなどのとり方を見直してみましょう。そしてすぐの効果は期待せず、また途中であきらめずに半年や1年かけて現在の体重を5~10%減らすことを目標にするとよいでしょう。
そしてダイエットを始める前に、食事記録をつけてみるのも良いでしょう。「水を飲んでも太る!」と考えている人ほど、無意識に食べている食品の多さに気がつくはずです。またダイエットや体重コントロールというと、すぐ極端に食事量を減らすことを考える方も少なくないと思いますが、食事のみよりも運動を併用するほうがより効果的です。食事内容を見直す上では、ご飯やパンなどの主食を減らしておかずを中心に食べる、ダイエット食品を利用するなどの偏った食生活ではなく、主食・副菜・主菜のバランスを考え、調理法や菓子・アルコールなどのとり方を見直してみましょう。そしてすぐの効果は期待せず、また途中であきらめずに半年や1年かけて現在の体重を5~10%減らすことを目標にするとよいでしょう。若い女性の「やせ」や無理なダイエットが引き起こす栄養問題
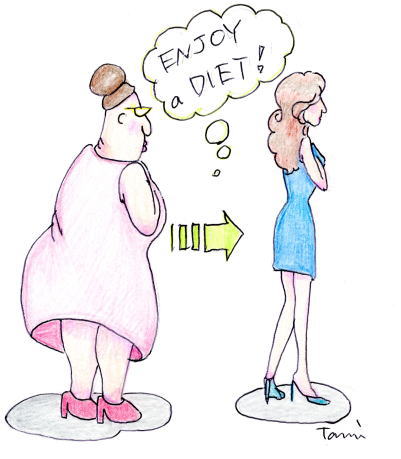 多くの若い女性が持つ「やせ願望」やダイエット指向。実はその多くの者がやせる必要がないのに、偏った食生活を送ったり極端なダイエットを繰り返しています。若い女性の「やせ」は多くの健康問題のリスクを高め、さらに若い女性や妊婦の低栄養問題は「次世代の子ども」の生活習慣病のリスクを高めると危惧されています。
多くの若い女性が持つ「やせ願望」やダイエット指向。実はその多くの者がやせる必要がないのに、偏った食生活を送ったり極端なダイエットを繰り返しています。若い女性の「やせ」は多くの健康問題のリスクを高め、さらに若い女性や妊婦の低栄養問題は「次世代の子ども」の生活習慣病のリスクを高めると危惧されています。若い女性で「やせ」が多いことは厚生労働省が毎年全国レベルで実施している国民健康・栄養調査で示されています。平成17年(2005年)に行われた調査によると、20年前(昭和60年)と比べて、肥満度(BMI)が18.5未満の「やせ(低体重)」が20代女性では5.8%・30代では14.2%・40代では4.2%増であることが分かりました。
女性の「やせ」が増えている背景には、食生活や生活スタイルの多様化・各種メディアに露出しているタレントがやせているため「やせているほうがいい」という価値観の普及・氾濫した様々なダイエット法など種々の因子が影響を及ぼしていると考えられています。そして誤ったダイエットなどによる偏った食生活は、鉄欠乏など潜在的な栄養不良のリスクを高めます。
鉄欠乏やそれに伴う貧血は、だるい・疲れやすいといった自覚症状や発育障害などをもたらします。鉄欠乏を防ぐには鉄を豊富に含む赤身の肉やほうれん草などの野菜をしっかり食べ、その吸収を高めるビタミンCなどを含む果物なども組み合わせて、バランスのよい食生活を送ることが大切です。月経のある20~40代の女性では、鉄は1日に10.5mgとると不足のリスクが少なくなると考えられていますが、実際には多くの女性で不足していることが指摘されています。無理なダイエットや偏った食生活は、鉄以外にも健康を維持する上で大切な栄養素の不足を招きます。また無理なダイエットを繰り返すと、逆に太りやすくなってしまうことが危惧されます。
さらに「やせ願望」が深刻化すると、「神経性食欲不振症(拒食症)」や「過食症」を招く恐れがあります。いずれも摂食障害ですが、前者は太ることを恐れて食物を避けるために極端な痩せを伴います。多くは思春期から青年期早期にかけて発症すると考えられています。後者は週に数回・数ヶ月間にわたる過食と、体重増加を防ぐための不適切な代償行動(嘔吐、下剤の使用など)の両方が存在し、拒食症よりは発症が遅い傾向があります。
摂食障害が慢性化すると、無月経や低血圧・不整脈など多くの健康障害を招く恐れがあります。摂食障害の要因には、強い「やせ願望」以外にも不安やストレスなど精神的な要因もあります。まずは適切な体重を理解し、誤った「やせ願望」を持たないようにしましょう。また食べること以外に、体を動かしたり趣味など持ってストレスを解消してみましょう。
最近の研究では、若い女性や妊婦の低栄養が、その子どもの将来の生活習慣病(高血圧・糖尿病など)のリスクを高めるとの見方があります。妊娠中のみならず、妊娠する前からの適切な食生活の確保が、将来の日本の子どもたちの健康にとって大切であることを理解し、適正体重の維持とバランスのとれた食生活の確立を目指しましょう。
(参照:厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト )
診察時間
Tami Clinic |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:30~12:30 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | |
| 午後 14:30~17:30 | / | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
| 午前 9:00~12:00 | / | ○ | / |
(休診日:日曜日・月曜日・祝日)※木曜、土曜は午前診療のみとなります。
〒640-8323 和歌山市太田1丁目13-10 太田ビル3階 多美クリニック
TEL 073-475-0010 ※和歌山駅東口から徒歩2分 <アクセス>
※「健康保健証」と、あれば「おくすり手帳」も忘れずにご持参ください。

<女性内科外来>
多美クリニック多美クリニック
〒640-8323
和歌山県和歌山市太田1丁目13-10
太田ビル3階 多美クリニック
TEL 073-475-0010
混雑により繋がりにくい場合は
TEL 080-5335-0010
<診療時間>
午前:9:30~12:30
午後:14:30~17:30
土曜日:9:00~12:00
休診日:日曜日・月曜日・祝日
※木曜日・土曜日は午前診療のみ。
予約優先制
<電話予約受付窓口>
午前 9:15~12:30
午後 14:15~17:30
土曜日 8:45~12:00
TEL 073-475-0010
混雑により繋がりにくい場合は
TEL 080-5335-0010
まで、お電話くださいませ。
(木曜日・土曜日は午前診療のみ)
※当日でもお電話頂ければ、待ち時間の少ない時間帯をご案内させて頂きます。ご予約がない場合、時間帯により待ち時間が長くなる場合がございます。予めご了承下さいませ。
(休診日:日曜日・月曜日・祝日)
![]()


感染症等の最新情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。
| 2026年2月 当院の診療カレンダー 休診日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 当院の診療カレンダー 休診日 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
診療時間
午前:9:30~12:30
午後:14:30~17:30
土曜日:9:00~12:00
(休診日:日曜日・月曜日・祝日)
※木曜、土曜は午前診療となります。
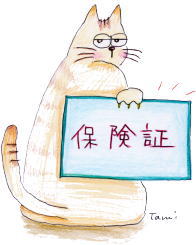
※「健康保健証」と、あれば「おくすり手帳」も忘れずにご持参ください。
更新日:2026.02.01